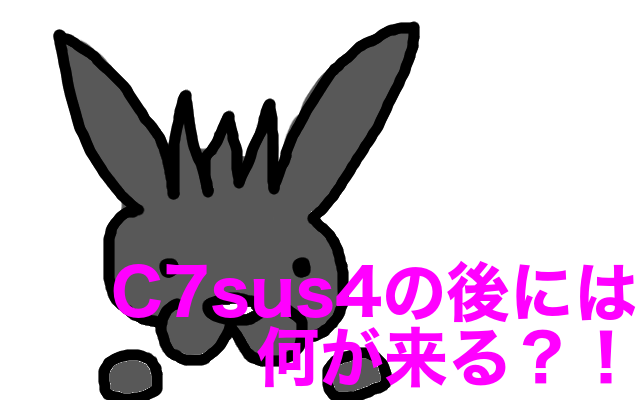【音楽】慶応義塾大学ワグネルソサエティのコンサートに行って感じたこと

実に!小学生の時以来に!クラシックのコンサートに行って来ました!
結論から言ってしまうとめちゃくちゃ良かったのですが、
今日はその中でも「アレンジ」更に言うと「作曲」と行った部分にフォーカスして
オケのコンサートに行ったからこそ感じた事を書きたいなと思います。
クラシックの曲と言うのは長い年月をかけて作られるものです。
教会や美術館に飾られているような美しい絵画のような美を感じました。
そしてそんな壮大な音楽に触れた時に自分のアレンジが少し恥ずかしく思えたのです。
もちろん4コマ漫画の中にも芸術はありますし
4コマ漫画と言う芸術に命をかけている方がいらっしゃるのも
存じ上げておりますし僕はそれも美だと思っております。
ただ、時間をかけて熟成して作られた芸術を前にして、
自分の書いた殴り書きの4コマ漫画のような楽譜を恥ずかしく思いました。
そもそもオーケストラって楽器も多いじゃないですか。
その分彩りも鮮やかで、本当に美しいアカペラの楽譜って
綺麗な水墨画なんだなと思わされました。
当たり前ですがアカペラは全て「声」と言う楽器を用いて奏でています。
それに対してオケって色んな楽器が居るんですよね。
だからこそ色が凄いなと思いました。
1人1人が違った音を奏でていて
それぞれがそれぞれで違う役割を受け持っていて
完全に音が生きているんですよ。
曲と言う世界の中で共生しているんです。
それぞれが曲と言う社会にそれぞれ違った形で貢献しながら
共に曲を営んでいるんですよ。
僕が今回聴いて来た「交響曲第1番 (マーラー)」と言う曲は
文字通りマーラーさんが手がけた1番目の曲だそうです。
この曲を書くのにかかった期間はなんと4年。
1884 – 1888にかけてつくられたそうです。
僕はこっちの知識は全然ないのでこの4年と言う年月が
長いのか短いのかはわかりませんが、
少なくとも僕が今までふれてきた音楽の中では
圧倒的に長い期間をかけて熟成された曲になります。
アカペラばかりやっていると
なかなか、いや、ほぼほぼ、こういう長い年月をかけて
作り込まれた音楽に触れ合う機会ってありません。
1曲の演奏時間は60分程度でしたが
その中でのストーリーのせめぎ合いもすごく
まるで長編小説を読んでいるかのような
不思議な時間を体感することができました。
何が言いたいかと言うとですね。
全般的に音楽をやっている人には
色んな音楽に触れ合って欲しいなと思います。
特に僕は今回はじめて物心がついてから
ちゃんとしたオケのコンサートに行きました。
やっぱりどんな音楽にそれぞれの美しさがありますし
そこに感化されたりそこから学ぶ事って沢山あります!
60分と言う演奏時間を長く感じさせない
じらしてじらしてじらしてじらして
最後の最後で魅せるクライマックス。
まさに音を介した興奮を体感しました。
この60分間の攻防ってアカペラや軽音楽では
まず体験することが出来ない音楽の美しさです。
長編小説のような、
はたまた長い年月をかけて書き上げられた1枚の絵画のような、
そんな美しい音楽に触れることが出来る素晴らしいコンサートでした。
※ここまで当たり前のようにオケの美しさについて書きましたが
演奏しているのが学生なのも凄い事です!
是非また行きたいなと思える素晴らしい公演でした。
[adsense]